本文
高知市議会だより200号(HTML版・平成28年3月1日発行)
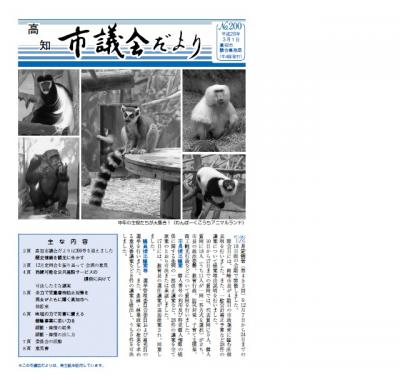
本文
1 12月定例会の概要
12月定例会(第453回)を12月7日から24日までの18日間の会期で開催しました。
開会日には、岡崎市長が4期目の市政運営に臨む所信表明を行いました。また、一般会計補正予算など28件の議案について提案理由説明を行いました。
10日から17日までの質問では、代表質問に5人、個人質問に18人(うち11人が一問一答方式を選択)が立ち、市長の政治姿勢、教育行政、防災対策、子育て支援策、商工観光行政などについて質問を行いました。
市長提出議案 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正議案など、28件の議案を全て原案のとおり可決または承認しました。
17日には、教育長の選任議案が追加提案され、同意しました。
議員提出議案等 選挙管理委員会委員および補充員の選挙を行いました。また、森林・林業政策の推進を求める意見書議案など8件の議案を提出し、うち5件を可決しました。
2 特集記事
高知市議会だよりは200号を迎えました
市議会だよりは、その前身の「高知市議会ニュース」として昭和24年1月に創刊されました。これは全国で6番目(行政広報・議会広報研究会調査)であり、また本市の行政広報(「高知市広報あかるいまち」の前身「市政ニュース」)の創刊よりも1カ月早い発行でした。
創刊号は、議会や委員会の開催状況の掲載に併せ、他都市が新設した税に関する情報やアメリカの都市と高知市の予算比較表など、GHQ(連合国軍総司令部)の施政下にあった当時の世相を反映した紙面構成でした。当時は公共施設のほか、理・美容室など集客が多い店などに置かれ、閲覧されていたようです。
以降、議会機関紙として議会の動きや地方自治に関する資料を提供するなど、市民を意識した「対外広報」として発行を続けてきました。
その後、昭和41年4月に紙面をリニューアルし、「高知市議会だより」第1号が創刊され、全戸配布となりました。それから50年が経過し、現在の発行部数は、約16万5000部となっています。
200号発刊に寄せて 広報委員長 浜口 卓也
現在の市議会において最年少である私がこのような機会をいただけたことに感謝しております。
市議会だより第200号と聞いて、これまでの本市議会の歴史に感服いたしております。
多くの諸先輩方が侃々諤々(かんかんがくがく)議論された結果が現在の高知市の姿であり、我々の議会での議論が、次に第300号に寄稿される議員にとって振り返るに値する歴史となるよう益々精進してまいります。
高知市議会だよりの変遷(年表)
◆昭和24年1月 「高知市議会ニュース」創刊(旬報)
◆昭和27年4月 「高知市議会週報」創刊
◆昭和31年9月 「高知市議会ニュース」復刊
◆昭和41年4月 「高知市議会だより」に移行
◆平成 3年2月 「高知市議会だより」100号発行
◆平成28年3月 「高知市議会だより」200号発行
3 質問および答弁
(1) 歴史情緒を観光に生かす
一年を通じて旬の食材が並び、観光客にも人気のある日曜市ですが、平成26年度に策定された「街路市活性化構想」に沿ってさまざまな見直しが実施されています。
また、29年は坂本龍馬没後150年、大政奉還から150年、翌30年は明治維新から150年という節目の年に当たり、本県では幕末から明治をテーマに博覧会が開催される予定です。
これらに取り組むことは、高知ならではの観光資源を磨き上げるとともに、「歴史観光」という新たな魅力を創出するチャンスでもあります。
【質問】街路市の出店基準の変更と、日曜市周辺の飲食店の充実について聞く。
【答弁】これまでは出店者を県内の生産農家または漁業者のみとしていたが、手作り食品や手作り工芸品等の製造者も選考の上で出店できるよう基準を緩和する。
このうち手作り食品は、自家製農産物または街路市で調達した食材を使った加工食品も対象とし、併せて、ストーブ等を使用して保温した食品の販売を28年1月から可能としたことから、その場で食べられる加工食品が増えるなど、利用者のニーズへの対応幅が広がるものと考えている。
また、周辺の飲食店に、営業時間を日曜市に合わせてもらうなど、日曜市と周辺飲食店舗が相互に連携して、集客人数の増加を図る取り組みにも着手している。
【質問】大政奉還150年、龍馬没後150年に向けた今後の歴史観光について聞く。
【答弁】大政奉還150年については、京都市が中心となって設立する記念プロジェクト連絡協議会に参画し、関係都市間で交流・連携事業等の協議を開始している。龍馬没後150年については、全国龍馬社中などの関連団体や関連都市と連携し、事業内容を検討していく。
また、龍馬の生まれたまち記念館や自由民権記念館などの本市所管施設でも、関連イベントの開催に取り組んでいく。
【質問】観光客にアピールする特色ある看板の設置について聞く。
【答弁】町の歴史や情報を観光客に分かりやすく発信するほか、高知ならではのデザインにするなど個性化を図ることや、QRコードなどを使って本市ホームページの観光情報を簡単に見られる機能を加えるなどの工夫を検討していく。
(2) 持続可能な公共施設サービスの提供に向けて~公共施設マネジメント~
本市では、高度経済成長に伴う都市化や人口増加を背景に、多くの公共施設を整備し保有してきました。しかし、これらの施設の中には、類似・重複しているものや市民ニーズの変化に伴い設置意義が薄れているものがあるなど、非効率な状況となっています。
さらに、建設後30年を経過した施設も多く、今後数十年の間に老朽化に伴う大規模な修繕や建て替えの時期を迎えることから、財政的にも大きな負担となることが予測されています。
公共施設は、行政サービスを提供するための基盤であることから、コスト意識や経営的視点を持って総合的に管理していく必要があります。
【質問】平成27年度中に策定を予定している公共施設マネジメント基本計画の案について聞く。
【答弁】同基本計画案では、施設の管理、機能、総量それぞれの最適化を図ることを基本目標としており、建設時だけでなく、維持管理も含めたコスト縮減を図っていく。平成28年度以降は、27年3月に作成した公共施設白書をもとに、各施設の機能や目的別の再編・再配置計画および長期修繕計画を順次策定していく。
数値目標としては、今後40年間で約30%の総量削減を掲げているが、公共施設には、災害時に避難所として活用されるものや、庁舎・消防署など公共サービスの根幹に関わるものもあるため、全ての施設を一律に削減するのではなく、施設機能の向上や用途の変更、近隣施設への複合化など、総合的に判断した上で取り組む必要があると考えている。
【質問】公共施設マネジメント基本計画にある環境配慮の視点をどのように進めるのか聞く。
【答弁】同基本計画案における機能の最適化の取り組みとして、安心して暮らせる環境を次世代に残すため、低炭素、循環型エネルギーの利用促進により環境負荷の低減を行うこととしている。
庁舎をはじめとする大規模施設については、今後建て替えや大規模改修を行う際、使用エネルギーの自動監視による制御や、データ収集による分析を行うことにより省エネルギー化につながるエネルギー管理システムの導入を検討することとしている。
また、その他の施設においても、日常点検マニュアルの整備など、省エネルギーによる環境保護に向けて取り組みを進めていく。
【質問】新たに建設する施設についての考え方を聞く。
【答弁】今後の公共施設の整備や運営については、直営や民営、指定管理等、多様な手法の検討が必要となる。
例えば、民間の資金や能力等を活用する手法として代表的なPFIについても、事業者が施設を建設した後、所有権の移転や運営・維持管理主体の移設時期によって、さまざまな事業方式に分けられ、国や他の自治体で導入されている事例もある。
海外の空港や港湾で導入されているコンセッション方式(施設所有権を行政に残し、運営を民間事業者が行う)など新たな手法もあることから、それぞれの施設の目的や機能を踏まえ、最善となる整備方法や管理・運営方法を検討していく必要がある。
【質問】本市の公共施設の約3分の1を占める学校教育施設の長寿命化計画の策定について聞く。
【答弁】公共施設マネジメント基本計画案では、28年度から施設点検を行い、将来コストを含め施設の状況を客観的に判断する材料となる施設カルテの作成に着手するとともに、29年度をめどに、それを基にした再配置計画や、長寿命化を含めた長期修繕計画といった実施計画を順次策定していくこととしている。
個別施設の長寿命化計画は、これらの実施計画に含まれる形で策定される予定となっており、学校教育施設の長寿命化計画については、さらに文部科学省から示された手引きに基づき策定していく。
(3) 全力で児童虐待防止対策を
平成27年10月に、本市において、生後10カ月の女児が虐待の疑いで死亡するという事象が発生しました。26年12月に発生した香南市での虐待死亡事件の検証報告がなされ、本市も対策を講じていた中での出来事であり、関係者に大きな衝撃を与えました。
【質問】子ども家庭支援センターの児童虐待対応について聞く。
【答弁】香南市での事件後、平成27年度から2名の人員増を行ったほか、県の支援を受けて、担当する全ケースの評価や支援方針の確認と見直しを行った。
27年8月には、要保護児童対策地域協議会の充実・強化のためにワーキングチームを組織し、同協議会実務者会議の運営の見直しを決定した。12月からそれらを試行実施しており、その状況を検証の上、28年度から本格実施していく。
また、専門的な研修や児童福祉司任用資格取得の講習会の受講など、職員の専門性を高める取り組みも一層進めている。
さらに、関係部署との庁内連携を図るほか、学校や保育所等への現場訪問を増やし、顔の見える関係づくりに積極的に取り組んでいる。
28年度には4名の人員増を図り、人員体制をさらに強化する。
【質問】本市版ネウボラ構想と児童虐待防止対策について聞く。
【答弁】同構想では、市内5カ所の地域子育て支援センターを拠点として、市内数カ所の中規模の子育て支援センター、そして各小学校区に1カ所以上の「集いの場」の3層構造による仕組みを整備する。これらの施設を保健師やNPO、ボランティアがパイプ役としてつなぐことで、地域の子育てにおける連続性や一貫性を持たせる。
「集いの場」は、子育て世帯が、地域の高齢者や子育て経験者と交流できる場であり、高齢者が子どもに昔遊びを教えることなどを通して世代間交流を目指していく。
こうした地域ぐるみの活動により、子育て世帯の不安や孤立感をなくすことが、児童虐待の発生予防や早期対応につながると考える。
【質問】児童相談所全国共通ダイヤル189の周知について聞く。
【答弁】本市では、公共施設へのポスター掲示のほか、虐待予防講演会やオレンジリボンキャンペーン、また児童に関わる学校や保育所、児童クラブで周知を図ってきた。また、庁内の人権研修では、虐待が疑われる際の通告義務も説明してきた。
今後も、市広報紙やホームページ、SNSを活用するなど効果的な周知を行い、いち早く連絡をいただくことで児童虐待防止につなげていきたい。
(4) 男女がともに輝く高知市へ
本市では、男女共同参画社会の実現を目指して「男女共同参画推進プラン(以下プラン)2011」を策定し、各種施策を推進してきました。
しかしこの間、社会環境の変化等によって多くの課題が顕在化してきたことや、女性活躍推進法の施行など、改めて注目される取り組みも始まっていることから、平成28年度からの5カ年計画となるプラン2016の策定に取り組んでいます。
【質問】本市の管理職に占める女性の割合について聞く。
【答弁】一般行政職における係長相当職以上の管理監督者に占める割合は、平成17年4月の14.3%から、27年4月は28.8%と、10年間でほぼ倍増している。
国の第4次男女共同参画基本計画案では、当該割合の目安として、市町村においては32年度末までに35%という割合が示されており、こうした成果指標も参考にしながら、庁内検討委員会の議論を経て、本市の目標を具体的に設定していく。
【質問】女性活躍推進法に基づく本市の取り組みについて聞く。
【答弁】同法の基本原則として、次の3つが挙げられる。
◆女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供およびその活用等が行われること
◆職業生活と家庭生活の両立を図るために必要な環境の整備により、それらの円滑かつ継続的な両立を可能にすること
◆女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと
以上を踏まえ、プラン2016と一体の計画として、市域全体の女性の職業生活における活躍について、推進計画を平成28年3月末までに策定する。
また、同法では、国や地方公共団体、労働者が300人を超える民間事業所の事業主に対して、女性採用の比率や勤続年数の男女差などの女性の活躍に関する状況の把握や、改善点の分析を踏まえた定量的な目標等を含む事業主行動計画の策定と公表が義務付けられている。
そのため、現在本市で策定している次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と一体の計画として策定するよう、庁内検討委員会による検討を開始しており、28年3月定例会にて計画案を報告する。
(5) 地域の力で災害に備える
消防団の活性化
東日本大震災等の経験から、南海トラフ地震などの大規模災害が発生した際、地域住民を守るためには、地域防災力が重要であり、その中心となるのが消防団です。
しかし、社会情勢の変化により、地域の防災活動の担い手確保が困難となっていることから、平成25年に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が制定されました。
本市でも消防団員不足と高齢化が課題となっています。
【質問】消防団員確保の取り組みと成果について聞く。
【答弁】平成11年度に消防団の関連事業を整理し、消防音楽隊や古式はしご乗り隊などの結成、あかるいまちへの特集記事の掲載、25年度からは消防団公式ホームページを開設し、活動内容の紹介や団員募集などの広報活動に取り組んでいる。
また、20年度には消防団協力事業所制度の導入により、事業所からの団員の加入と活動促進を図り、21年度には女性団員の環境づくり検討会などを設置し、女性も含めた消防団員確保に取り組んでいる。
こうした取り組みの結果、消防団員数を10年前と比較すると、全国的に6%程度減少している中、本市は3.3%増加している。
【質問】消防団員の後継者育成の取り組みについて聞く。
【答弁】幼少時から地域防災に関心を持ってもらい、消防団活動を理解してもらうことが、後継者育成につながると考えており、平成12年度から地域の小・中学生の協力により、22カ所の分団屯所のシャッターへ防災に関するペイントを実施してきた。
また、市内の全公立中学校の2年生を対象とした救命講習に消防団員が出向くなど防災意識の啓発、向上に努めており、今後も地域の防災訓練やイベントを通じて後継者育成に取り組んでいく。
公民館、集会所の耐震化
公民館や集会所は、町内会等の社会教育やコミュニティ活動の拠点であるとともに、地域の防災活動面においても重要な施設であるため、耐震化が急務となっています。
【質問】本市の公民館、集会所の現状について聞く。
【答弁】平成25年度現在で、地域住民が費用を負担して建設した自治公民館が184館、集会所等が87館存在しており、その半数以上が新耐震基準に適合しないと推測されている。
【質問】耐震化の取り組みについて聞く。
【答弁】本市には、公民館等の改修を行う場合に事業費の60%を補助する制度があり、避難所機能を付加することで県の補助制度も活用できることから、地域住民の意向を踏まえ、耐震改修を進めていきたい。
(6) 競輪事業に若い力を
競輪事業は、全国的に車券売上高が激減しており、大変厳しい経営状況が続いています。
本市も同様の状況でしたが、モーニング競輪を開始するなど経営改善に取り組んだ結果、平成23年度以降は単年度黒字を確保し、27年度も約1億7千万円の黒字の見込となっています。
今後も競輪事業を継続していくためには、地元選手の育成強化が必要であり、自転車競技の裾野を広げる取り組みが重要となっています。
【質問】競輪選手の人材育成の取り組みについて聞く。
【答弁】選手の育成強化は、現役の競輪選手で構成される選手会に、また、選手の発掘育成は、新人の指導を行っている高知県自転車競技者育成会に補助金を交付し、活動の支援を行っている。
地元出身の選手が出場するレースは大きく盛り上がるとともに、来場者数や車券売上の増加も期待できるため、継続的な支援が必要であり、関係団体や指導者と協議しながら、より効果的な支援を検討していく。
【質問】自転車競技の裾野を広げる取り組みについて聞く。
【答弁】競技用自転車が高価であることや指導者不足などから、市内に自転車競技のクラブ活動をしている高校は4校しかない。そのため、本年度中に練習用自転車を高知競輪場に複数台配置し、競輪選手やOBの指導を直接受けられる環境整備を行っていく。
4 休憩室
丙申(ひのえさる)の年頭に拙句を御披露します。
国憂い 志士らが散った 夜明け前 時を超え今 我立ち向かう
今から150年前の1866年、旧暦の1月21日に薩長同盟が成立、翌年末に坂本龍馬暗殺、大政奉還、王政復古の大号令があり、この時期はまさに時代の転換期「夜明け前」でした。
その立役者の中に郷土の若き志士たちが多くいたことを、私たちは誇りに思うとともに、新しい政治・社会体制を見ることなく散っていった彼らの悔しさに思いをはせなければなりません。
ところで、今夏の参議院議員選挙から「18歳選挙権」が実施されます。あらゆる選挙で投票率が低下し続ける中、この制度変更の影響に注目したいと思います。
選挙の低投票率化や政治への無関心は、民主主義の腐敗の始まりとも言われますが、既に看過できない状況となりつつあります。
龍馬が船中八策で示した「上下議政局ヲ設ケ、議員ヲ置キテ万機ヲ参賛セシメ、万機宜シク公議ニ決スベキ事」を実践するためにも、一国民として責任ある一票を投じたいものです。 (議会広報委員 清水おさむ)
5 12月定例会を振り返って(会派の意見)
市民クラブ
子ども・子育て支援新制度へ 高知市は全力投球を!
竹内千賀子議員は、南海地震対策や保育士不足による待機児童解消のための賃金・処遇改善、食物アレルギー対応の調理員の加配等を中心に代表質問を行う。
待機児童対策は最優先課題であり、臨時保育士の賃金改善は重要。食物アレルギー対応については、一定の基準を定め、加配職員の配置について検討を進めているとの答弁を得た。
岡崎邦子議員は、安保関連法および伊方原発再稼働について、市長に人としての姿勢を問う。
また、厳しい環境で学ぶ本市の中学生に対する「学力向上」の取り組みについて、中でもチャレンジ塾の存在価値を評価し、さらなる拡充を求めた。
長尾和明議員は、自転車競技の競技力向上について問う。
また、南海地震対策に関し、不足する収容避難所の確保策については、定住自立圏を形成する南国市、香美市、香南市と協議を進めているとの答弁があった。
岡崎豊議員は、資金収支の健全性、自立性、行政効率の状況から、今後の事業計画における財政面での整合性を求めた。
また、高知西高校の国際バカロレアの認定準備に触れ、松原教育長は「子どもたちの学習意欲が向上し、意義深い」と答弁した。
新風クラブ
事業運営力に疑問有り、指定管理者議案に反対票を投じる!
・代表質問 中澤はま子議員
良質な石灰石産地の本市において、既存鉱山の枯渇が懸念される中、鏡地区の新たな石灰鉱床の開発についてただした同議員に対し、市長は「指摘のとおり、鉱床開発で発生する大量の土砂は、南海トラフ地震で被災した堤防の復旧や地盤沈降の埋め戻しにも役立つ。産業振興に加え、災害復旧の面からも重要であり、県と連携して支援する必要がある」と答えた。
・個人質問 吉永哲也議員
鏡地区における保育所と幼稚園の認定こども園化について、執行部は「同地区では、既に保育所と幼稚園が行事運営などで連携しており、認定こども園となる可能性は十分にある。今後、保護者や地域住民の理解を得ながら検討していく」と答えた。
・個人質問 水口晴雄議員
小中学校の校区見直しの進捗(しんちょく)状況について、教育長は「検討委員会は2月に報告書をまとめる予定だが、小学校は12学級以上、中学校は6学級以上を目指すとともに、一つの小学校から同じ中学校へ進学する校区割りが望ましい」と答えた。
日本共産党
子ども医療費小学卒まで無料へ、道のない所に「道の駅」追及
市長選の争点や会派の来年度予算要望事項に基づき、代表質問に迫哲郎、一般質問に浜口佳寿子、はた愛、細木良、岡田泰司の各議員が登壇。
厳しい財政運営と言いながら今後の財政計画は示さず、新庁舎や東部総合運動場多目的ドームの建設等大型事業が急増したことを指摘。
市民負担増で改善した財源は、まず暮らし充実に回すよう求めたが、子ども医療費無料化は平成28年10月から小学校卒業まで拡充するものの、市長選で言及した中学校卒業までは、希望であり公約ではないと否定。
高すぎる国保料減免は国の責任と冷たい答弁。都市計画マスタープランの改ざんや事業主不在の官民連携など特定業者が調査区域の約9割を所有する浦戸「道の駅」構想の問題が浮き彫りに。
介護保険法改正に伴う訪問・通所介護等の新総合事業への28年10月移行で必要なサービス確保と、公共調達条例に基づく賃金下限額が低すぎて、条例の効果が発揮されていない問題の早期改善を求めた。
マイナンバー施行に対し、市民に不利益とならない取り組みを要望。
公明党
岡崎市政4期目に政策提言 市民生活を守る公明党の主張
代表質問に立った山根堂宏議員は、4期目の市長の施政方針について質問を行い、将来を見通した財政運営と時代に即応した特色ある政策展開を求めました。
高木妙議員は、津波避難ビル指定の高さ要件の見直しについてただしました。今後は、一定の要件を満たした上で、ガイドラインの見直しが図られることとなりました。
大久保尊司議員は、マイナンバー制度において、市民に負担を生じさせない取り組みを求め、十分配慮するとの答弁を得ました。
伊藤弘幸議員は、かねてからの課題である鉛製給水管撤去について質問。上下水道局から、所有者への情報提供を検討するとの答弁を得ました。
寺内憲資議員は、御畳瀬地区に保安上危険な空き家が多いことから、行政代執行も見据えたスピード感のある対応を市長に求めました。
新こうち未来
自由民権記念館指定管理者選定議案に反対。地元企業の育成を!
今定例会に提出された自由民権記念館指定管理者選定議案に反対。代表質問、経済文教委員会および本会議における採決と、一貫してその疑義を唱えた。
公平公正な選考の結果、県外企業が選定されたということであるが、高知市が地元企業に対する研修など、育成面を長年怠った状態で本議案を提出してきたことへの警鐘であった。
今後は現状に満足せず、市民とともに向上を目指す組織へと変革することを期待する。
代表質問では、会派代表の戸田二郎議員が、旭町付近の狭い国道の改良や教員異動調書の不祥事問題を指摘した。
個人質問には氏原嗣志議員、川村貞夫議員、福島明議員、浜口卓也議員の会派全員が登壇した。
みどりの会
近森議員の質問に成果が続々
ふるさと納税が2億円を超える。
残業手当580万円を指摘する。
大型映像装置の整備を決定する。
日曜市への新規出店が可能に。
土佐の上海蟹ツガニを市が支援。
生鰹の店舗を観光客にアピール。
自動販売機の契約変更で利益増。
SNS教育でスマホの達人育成。
6 12月定例会で結果の出た請願・陳情
採 択
◆事務取扱要綱に基づく適正な事務を求める件
不採択
◆伊方原発の再稼働を行わないことを求める意見書提出の件
◆災害時におけるミニ放送局の制度緩和に関する件
◆市道建設時の土地売買契約書の件
7 12月定例会に提出した意見書
全会一致で可決した意見書
⑴森林・林業政策の推進を求める意見書
森林は、木材等の供給や二酸化炭素の吸収など、国民の安全・安心、国土、環境を守る重要な財産であるが、林業関連産業の現状は、経営基盤が依然として脆弱であり、山村の疲弊も著しい状況にある。
こうした中、平成27年3月に山村振興法が改正され、地域の特性を生かした産業の育成による就業機会の創出や定住の促進等が新たに基本理念に盛り込まれた。これらを踏まえ、山村地域の再生や地域経済の活性化を図るために、森林・林業施策の推進は急務であり、立地条件に対応した森林整備や間伐材等の利活用、適切な治山対策、鳥獣害対策の実施等が重要となっている。
よって、木材自給率50%以上の達成に向け、地域材を利用した公共建築物の木造化、新たな木材利用の創出および木質バイオマス等の利用促進を図るとともに、地域材および認証材の計画的供給、販売体制の確立を図ることなど6項目の実現を国に強く要請する。
賛成多数で可決した意見書
⑵空き家の発生を抑制するための税制改正を求める意見書
南海トラフ地震対策においては、旧耐震基準で建築された家屋の耐震化促進が大きな課題となっており、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたが、新たな空き家を発生させないための政策誘導力の弱さが指摘されている。
居住用家屋が空き家化する契機は相続時が最も多く、相続人は不可避的に空き家の管理経費を負担する必要に迫られることから、税制上の優遇措置が必要である。
よって、旧耐震基準で建築された居住用家屋については、相続後、一定期間内に耐震リフォームまたは除却を行った場合、費用の一部を所得税額から控除する制度の新設や、その後に家屋を売却した場合の税制上の優遇措置を検討するよう政府に強く要望する。
⑶マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書
マイナンバー制度の導入に伴い、市町村には通知カードと個人番号カードの交付について対応するよう求められている。
市町村のカード交付事務に係る経費については、個人番号カード事務費補助金が措置されるが、本来、全額国庫負担であるべきところ、非常に低い補助上限額となっているため、市町村は財源負担を強いられることとなっている。
また、平成28年度以降についても相当数の交付が見込まれるが、現時点では、これらに対して十分な補助金額が確保されるのか明確にされていない。
よって、28年度以降についても、地方公共団体情報システム機構に支払う交付金全額を国の負担とし、十分な予算措置をすることなど6項目について、政府に特段の配慮を求める。
⑷地方大学の機能強化を求める意見書
国立大学の運営費補助金は年々削減され、教育の質の低下や将来的な学生定員数の削減につながりかねない状況にあり、地方創生に向け、地域と大学がこれまで以上に積極的に取り組もうとする中、若者の地元定着や、地域のニーズに対応した人材育成など、地方大学の果たす役割に大きな影響が出てくることが懸念される。
よって、地方で若者が一定水準の専門知識を習得できるよう教育の質の確保を図るとともに、大学で学ぶ学生定員確保のため、その基盤となる国立大学法人運営費交付金の充実、私立大学に対する私学助成の拡充を図ることなど3項目について、強く推進するよう政府に求める。
⑸夜間中学の整備と拡充を求める意見書
全国夜間中学校研究会の推計によると、15歳を過ぎて義務教育が修了していない者は、百数十万人にも上るとされている。
現在、夜間中学は全国8都府県に31校しかなく、四国や九州には1校もない。また、夜間中学がある地域においても、市内在住、もしくは市内での正規就労6カ月以上などの入学要件があり、市外に住む者の就学の機会が制約されている状況がある。
また、夜間中学在籍者のうち、外国人が占める割合は8割を超え、日本の義務教育を終えていないために就職や進学ができず困っている者も多く、日本に住み、日本語を学びたい外国人に対応した整備と拡充が求められる。
このような現状に適切に対応することで、地域の活性化、治安の改善にも資すると考えられる。
よって、義務教育未修了者や在留資格を持つ外国人が、夜間中学の情報を入手しやすいように配慮した広報の展開や、低所得者に対する授業料減免などの誘導策を推進することなど3項目について、迅速な対応を政府に求める。
否決した意見書
⑹複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書
⑺国立大学学費の連続値上げに直結する運営費交付金を削減しないことを求める意見書
⑻国民監視社会をつくる共謀罪を導入しないことを求める意見書
8 人事議案等
12月定例会中の17日に教育長の選任議案が提出され、同意しました。
また、最終日の24日に選挙管理委員会委員、同補充員の選挙を行い、指名推選により当選者を決定しました。
教育長
横田 寿生(よこた としお)
選挙管理委員会委員
稲田 良吉(いなだ りょうきち) 木藤 善治(きとう よしはる)
友永 善惠(ともなが よしえ) 新名 實(にいな みのる)
同補充員
山中 信雄(やまなか のぶお) 清遠 綾子(きよとう あやこ)
長澤紀美子(ながさわ きみこ) 松岡 章雄(まつおか あきお)
9 委員会の活動(11月1日から1月31日まで)
常任委員会
経済文教委員会
12月4日
政策・施策評価について対象施策選定の協議を行いました。
12月定例会
18日に、平成27年度産業立地推進事業特別会計補正予算など8件の議案の審査を行いました。
青年センターおよび自由民権記念館の指定管理者の指定に関する議案2件は全員反対で否決し、その他の議案はいずれも全員賛成で可決しました。
また、平成27年度教育委員会の事務の管理および執行の状況の点検および評価結果報告書など4件の報告を受け、併せて政策・施策評価について対象施策のヒアリングを行いました。
1月19日
政策・施策評価について議会意見の協議を行いました。
厚生委員会
12月3日
政策・施策評価について対象施策選定の協議を行いました。
12月定例会
18日、21日に、医療安全推進協議会条例の一部改正議案など5件の議案の審査を行いました。
国民健康保険条例の一部改正議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決しました。
また、高知市新型インフルエンザ等対策行動計画について報告を受け、併せて政策・施策評価について対象施策のヒアリングを行いました。
1月12日
政策・施策評価について議会意見の協議を行いました。
1月18日~20日
東京都世田谷区にて、産後ケア事業など3項目、荒川区にて、要保護児童対策地域協議会、埼玉県川口市にて、成人歯科健診、兵庫県神戸市にて、救護施設の管理運営の視察を行いました。
建設環境委員会
12月2日
政策・施策評価について対象施策選定の協議を行いました。
12月定例会
18日、21日に、都市公園条例の一部改正議案など5件の議案と陳情1件の審査を行い、いずれも全員賛成で可決し、陳情1件の結果を出しました。
また、第1回高知市上下水道事業経営審議会の報告についてなど3件の報告を受け、併せて政策・施策評価について対象施策のヒアリングを行いました。
1月18日
政策・施策評価について議会意見の協議を行いました。
1月28日・29日
茨城県にて、浄化槽の一括契約、神奈川県平塚市にて、路面下空洞調査、都立小平霊園にて、同霊園の運営について視察を行いました。
総務委員会
12月2日
政策・施策評価について対象施策選定の協議を行いました。また、高知市男女共同参画推進プラン2016(原案)について報告を受けました。
12月定例会
18日、21日に、津波避難センター条例の一部改正議案など13件の議案と、請願1件、陳情2件の審査を行いました。
平成27年度一般会計補正予算、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正議案、収入証紙条例の一部改正議案、税条例の一部改正議案、新市まちづくり計画の一部変更に関する議案2件の計6件は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決または承認し、請願1件、陳情2件の結果を出しました。
また、とさでんモニタリング会議の報告など2件の報告を受け、併せて政策・施策評価について対象施策のヒアリングを行いました。
1月19日
政策・施策評価について議会意見の協議を行いました。
特別委員会
行財政改革・新庁舎整備調査特別委員会
11月19日
公共施設マネジメント基本計画(案)についてなど3件の報告を受けました。
南海地震等災害対策調査特別委員会
11月18日~20日
宮城県東松島市にて、あおい地区まちづくり整備協議会、女川町にて、まちなか再生計画、石巻市にて、東日本大震災の復興状況、名取市にて、閖上(ゆりあげ)地区まちづくり協議会の視察を行いました。
10 高知市議会からのお知らせ
(1)録画DVDの貸し出し
本会議の中継放送を録画したDVDの貸し出しを行っています。
貸し出し準備に時間を要するため、ご希望の方はあらかじめ、議会事務局までお申し込みください。
電話823-9400
(2)インターネットによる本会議の録画配信
過去1年間の本会議(定例会)について、インターネットで配信しています。
高知市ホームページから議会中継(録画)専用ページに入ると視聴できます。
会議日や質問議員名、発言内容の語句等からの検索も可能です。
(3)請願・陳情の出し方
市の行政などに対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情はその必要がなく、審査は請願と同様に取り扱われます。
文書は市議会議長宛てに1通提出してください。
なお、定例会ごとに締め切りがあり、それを過ぎた場合は次の定例会からの審査になりますので、ご注意ください。
請願(陳情)書の記載例
○年○月○日 高知市議会議長 ○○ ○○ 様 (代表者の)住所○○○○○○○○○○○○ (代表者の)氏名 (個人の)印 紹介議員氏名 印 ※ 陳情は紹介議員不要です。 ○○○に関する請願(陳情) . 趣旨・理由
|
(4) 会議録の閲覧
12月定例会本会議の会議録は3月上旬にできる予定です。
本町仮庁舎1階の情報公開センター、同6階の議会図書室でご覧になれます。
また、高知市ホームページ上で、本会議は平成6年12月定例会以降、委員会は16年4月以降の会議録をご覧いただけます。
11 会派の構成と電話・ファクス番号
市民クラブ (8人)☎823-9402 FAX 802-3055
新風クラブ (7人)☎823-9401 FAX 871-2811
日本共産党 (7人)☎823-9404 FAX 823-9558
公 明 党 (6人)☎823-9403 FAX 871-2485
新こうち未来(5人)☎823-9406 FAX 822-8119
みどりの会 (1人)☎823-9476 FAX 823-9350※
※議会事務局直通のファクス番号です



