本文
歴史万華鏡コラム 2025年10月号
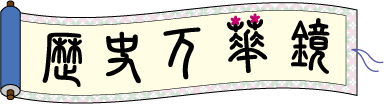
高知市広報「あかるいまち」より
寺田寅彦の研究と牧野富太郎

(牧野富太郎 書)
多方面に活躍したことから「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と呼ぶ人もいる寺田寅彦(1878~1935年)は、研究面では日本の「X線結晶学の元祖」ともいわれる業績を残した。大正2(1913)年には「X線と結晶」という論文を『ネイチャー』に掲載するも、イギリスのブラッグ親子が同様の研究を同誌上で発表した直後であった。ブラッグ親子は大正4(1915)年に「X線による結晶構造解析に関する研究」によってノーベル物理学賞を受賞している(当時は、海外への郵送は船便であり、ずいぶん時間がかかったらしい。残念なことである)。
また、大正12(1923)年の関東大震災の直後には震災の被害状況や震災火災の調査に尽力し、精力的に活動した。そして予知は難しいとの立場から警鐘を鳴らし続けている。一連の活動の中で「天災は忘れられたる頃来る」という名言が生まれたとされるのは一番弟子の中谷宇吉郎博士(世界初の人工雪の研究開発者)の証言によるものである。
その後は、東京帝国大学の教授となり、実験物理学や地球物理学の講座を担当した。また地震研究所や航空研究所、理化学研究所等で重要な研究に携わり、若い研究者たちに多くの示唆を与え続けた。「ねぇ君ふしぎだと思いませんか」は博士の口癖であったようだ。
高知市の寺田寅彦記念館の入り口に牧野富太郎博士の文字が刻まれた石碑がある。「寺田寅彦先生邸址」と「天災は忘れられたる頃来る」である。昭和27(1952)年の揮毫である。寺田博士は『随筆難』という作品の中で「『常山の花』と題する小品の中にある『相撲取草』とは邦語の学名で何に当るかという質問を受けて困ってしまって同郷の牧野富太郎博士の教えを乞うてはじめてそれが『メヒシバ』だということを知った」という記述を残している。お互いに尊敬し合っていたとも伝えられる両者の交流が伺える一文であり、NHKの連続テレビ小説『らんまん』の中に登場してもおかしくない逸話だったかと思われる。
寺田寅彦記念館友の会 宮 英司
広報「あかるいまち」 Web版トップ > 歴史万華鏡コラム もくじ
※このページは、高知市広報「あかるいまち」に掲載されている「歴史万華鏡」のコーナーを再掲したものです。



