本文
歴史万華鏡コラム 2025年05月号
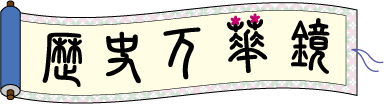
高知市広報「あかるいまち」より
立志社の「志」

立志社の創立は今から151年前の明治7(1874)年4月。同年1月に、本市出身の板垣退助は、副島種臣らとともに政府左院へ「民撰議院設立建白書」を提出し、早期国会開設を求めたが受け入れられず、帰郷。高知で片岡健吉や林有造とともに同志を集めることにした。これが立志社である。
創立当時、立志社では二つの趣意書がつくられた。植木枝盛の『立志社始末記要』には、最初の趣意書は「四方ニ示サレ」、次の趣意書は「四方ニ頒わケラレ」とあり、その目的が異なっていたことがうかがえる。ここでは、それぞれの内容を簡単に紹介する。
一つ目の趣意書は「世運ノ上進スル人民ノ奮励スル相視ズンバアル可カラズ」で始まる。日本社会の現況や政府のあるべき姿、また民会を立てることの必要性など立志社の「志」を示すものであった。立志社の結社の目的は人民の権利の伸張による社会の幸福実現にあるとされ、そのためには一人一人が自分の権利を自覚すること、恒産を得て自立することが必要であると記されている。
二つ目の趣意書の始まりは「西人云ヘル事アリ、自主ハ智識ニ本ヅキ政事ハ自主ニ立ツ」。政治に参画するためには自主が必要であり、自主のためには知識が肝要であるというのだ。ところが、現在の日本では元々知識気風を備えていたはずの士族でさえ、明治以降常職を失い、自主を失おうとしていると指摘。士族が勤勉によって恒産を得ること、四民が互いに協力し合って知識気風を上進することが四民ひいては国家人民の利益福祉となると説かれている。実際に立志社では生活に困窮していた士族を救うための士族授産や、教育施設としての立志学舎の設立・運営が行われた。
趣意書からうかがえる立志社の基本的な考え方──社会の幸福のためには人々の政治参加が必要であり、政治参加のための知識をつけなければならない、そして知識を備えるためにはまず生活の安定が欠かせない──これは、現代の我々にも示唆をもたらすものではないだろうか。
自由民権記念館 学芸員 汲田 美砂
広報「あかるいまち」 Web版トップ > 歴史万華鏡コラム もくじ
※このページは、高知市広報「あかるいまち」に掲載されている「歴史万華鏡」のコーナーを再掲したものです。



