本文
高知市議会だより201号(HTML版・平成28年6月1日発行)
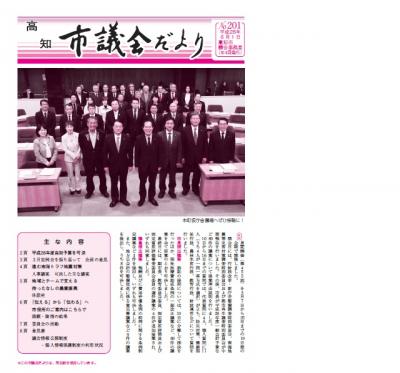
本文
1 3月定例会の概要
3月定例会(第455回)を3月7日から25日までの19日間の会期で開催しました。
開会日には、行財政改革・新庁舎整備調査特別委員会、南海地震等災害対策調査特別委員会および都市再生調査特別委員会が中間報告を行いました。その後、市長が平成28年度一般会計予算など89件の議案について提案理由説明を行いました。
10日から16日までの質問では、代表質問に4人、個人質問に11人(うち4人が一問一答方式を選択)が立ち、防災対策、健康福祉行政、農林水産行政、教育行政、財政運営などについて質問を行いました。
市長提出議案 訴訟の提起については、10日に分離して採決を行ったほか、福祉医療費助成条例の一部改正議案など、89件の議案を全て原案のとおり可決しました。
最終日には、副市長、教育委員会委員、固定資産評価員および固定資産評価審査委員会委員の選任議案の4件が追加提案され、いずれも同意しました。
議員提出議案 報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案など3件を提出し、いずれも可決しました。
また、地方公会計の整備促進に係る意見書議案など9件の議案を提出し、うち8件を可決しました。
2 平成28年度当初予算を可決 ~夢と希望にあふれる「にぎわいと暮らし安心のまちづくり」~
3月議会には、平成28年度一般会計予算など23件の予算議案が提出され、全て原案のとおり可決しました。
28年度当初予算は、南海トラフ地震対策や子育て支援策をはじめとする安全・安心のまちづくりを最重点に置き、総合計画第2次実施計画に登載された実施事業を着実に推進することを基本に、地域や市民の暮らしに密着した事業を中心にした編成となっています。
一方で、今後5カ年で59億円程度の財源不足が見込まれており、行財政改革の継続や投資事業の平準化等により収支の均衡を図る必要があります。
当初予算市長説明要旨
地方創生の推進
地方創生については、27年10月に策定した「高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に、連携中枢都市圏や「生涯活躍のまち」の形成に向けた取り組みなど新たな事業を追加し、国の支援制度を積極的に活用しながら推進していく。
また、移住・定住の促進については、三世代同居等Uターン支援事業補助金の新設や、高知中央広域定住自立圏を構成する南国市・香南市・香美市と連携し事業を進める。
南海トラフ地震対策
津波避難対策は、避難施設や避難路を活用した避難訓練の実施などより実践的に進める。
また、主要な避難所となる市立学校のヘリサインについては、長期浸水区域内の学校から優先的に整備を進め、29年度中には整備を完了させる。
さらに、学校施設や保育所の耐震化を推進する。
介護予防と総合事業
介護保険法の改正により、要支援1、2の方の訪問介護および通所介護は、市町村が実施する総合事業に移行となる。本市では、訪問型サービスの新設や通所型デイサービスの創設を目指し準備を進めている。
併せて、包括的支援事業の充実に向け、認知症初期集中支援チームの設置など3事業を新たに開始する。
これらの事業を着実に実施し、住み慣れた地域において誰もが安心して暮らせる地域包括ケアシステムの構築を進める。
子ども・子育て支援
子どもの医療費については、28年10月から通院・入院の全額助成を小学6年生までに拡充するとともに所得制限を撤廃し、子育て世帯の経済的負担軽減を図る。
また、切れ目のない子育て支援を実現するため、本市版ネウボラ構想の策定に取り組む。
教育施策
学力向上対策では、中学校放課後学習支援員を16中学校に配置し、学習意欲および学力向上のための学習支援を行う。
中学校給食については、給食センター建設工事の早期着工を目指し、30年度中の完全実施に向けて精力的に取り組む。
観光振興
今後、増加が見込まれる外国人旅行者が、より快適に本市で滞在できるよう、WiFi 環境の整備など受け入れ態勢の充実を図る。
また、29年は大政奉還150年、龍馬没後150年の節目の年であり、翌30年が明治維新150年となることから、歴史資源の磨き上げを行う。
3 質問および答弁
(1) 進む南海トラフ地震対策 ~東日本大震災発生から5年~
津波・長期浸水対策
本市における津波浸水対策は、その地理的特性から、高知新港沖、浦戸湾湾口部、浦戸湾内部の護岸の3つのラインによる防護(三重防護)が重要となります。
しかし、この対策には、多額の経費と高度な技術力を要することから、国に対し直轄事業による整備を求めています。
【質問】三重防護の内容と、その効果について聞く。
【答弁】三重防護は、(1)高知新港沖の防波堤の延伸・かさ上げ・粘り強い構造への改良(2)浦戸湾湾口部への固定式構造物の設置と、外縁部防潮堤の液状化対策や粘り強い構造への改良(3)浦戸湾内部の護岸などの液状化対策や粘り強い構造への改良の3つのラインでの対策により、津波から防護するものである。
既に、国の直轄事業により進められている高知海岸などの整備と合わせて、三重防護が完成すれば、甚大な被害をもたらすL2クラスの地震の津波に対しても、津波による人的・物的被害および長期浸水が大幅に軽減でき、復旧復興を迅速に行うことが可能になると考える。
【質問】長期浸水被害地域における救助・救出対策について聞く。
【答弁】本市では、長期浸水が想定される地域の住民に対し、避難を考えている場所や経路、家庭での備蓄状況などの事前の備えについて、防災意識調査を平成28年度に実施する。
また、県においては、本市の調査結果も活用しながら、個々の避難速度の違いや建物倒壊による避難の遅れ等を加味した津波避難シミュレーションを実施し、住民の避難対策および救助・救出対策の基礎資料とする。
これらの結果を踏まえ、各地区の津波避難計画の検証や見直しを行い、各種防災訓練へ活用していくとともに、自衛隊や警察、消防などの関係機関と連携し、救助・救出対策を取りまとめていく。
【質問】救助用ボートの配置計画について聞く。
【答弁】長期浸水地域では、濁水のため水面下の障害物や水深が確認できないことや、大量のがれきの浮遊が想定されるため、水面下に推進装置のないボートが有効であると考えており、平成28年度に長期浸水地域を管轄する消防分団に、ジェット船外機を備えたウレタンボート8艇を配置する予定である。
また、国からは、冠水地域において走破性の高い水陸両用バギーやフローティング担架等の救助資機材を積載し、冠水地域での人命救助に特化した津波・大規模風水害対策車両が無償で配備される予定である。
地域の防災力向上対策
本市は、災害対策の柱の一つに「地域の防災力向上」を掲げています。その具体的な方策として、地区防災計画の策定があります。
地区防災計画は、平成25年の災害対策基本法の改正において、地域の共助による防災活動の推進の観点から内閣府が創設した制度で、本市では、下知地区がモデル地区の指定を受け、計画づくりが進められています。
【質問】本市における地区防災計画の策定支援について聞く。
【答弁】下知地区では、平成27年度から3年間で、災害から命を守る・命をつなぐ・生活を立ち上げる対策についての具体的な活動方針を地域全体で検討する計画となっているため、28年度からの2カ年も支援を継続する。
他の地域では、自主防災組織連絡協議会や小学校区単位の連合会などを通じ、下知地区の取り組みを紹介しながら、地区防災計画の策定の拡大につなげていきたい。
防災教育の推進
【質問】本市の中学校における防災教育について聞く。
【答弁】南海中学校では、生徒による防災活動組織であるNSP(ナンカイ・サバイバル・プロジェクト)を中心に、生徒が現地調査を行い作成した地区別避難場所一覧を地域に配布したり、地域の会合等で啓発を行うなど、学校と地域が連携して地震・津波防災についての課題を共有し、生徒の主体性や行動力を引き出す防災教育を展開している。
こうした取り組みが高く評価され、平成26年度のぼうさい甲子園において津波ぼうさい賞を受賞し、28年2月には、内閣府から防災教育チャレンジプランの実践団体に選定された。
南海中学校の取り組みは、教育委員会が行う各種研修や実践発表により周知され、他の中学校でも「助けられる人から助ける人へ」という意識改革のもと、防災教育に取り組まれている。
(2)地域とチームで支える ~認知症カフェ拡充に向けて~
全国の認知症高齢者数は、平成24年時点で約462万人と推計されており、10年後には約700万人までふえる見通しとなっています。認知症の方が住みなれた地域で暮らし続けるためには、本人と介護する家族への直接的な支援はもちろんのこと、地域で支えていく仕組みづくりが必要です。
国が策定した認知症施策総合戦略、いわゆる新オレンジプランにおいても、早期対応に必要な体制整備として、各市町村に認知症初期集中支援チームの設置を推進することが掲げられています。
【質問】認知症カフェの運営や設置状況について聞く。
【答弁】本市で開設されている認知症カフェは、民間事業者による運営が5カ所、民家を活用した住民主体の運営が2カ所となっているが、全国的には社会福祉法人やNPOによる運営が約半数となっており、スタッフの半数は専門職以外の方である。
本市では、平成27年度から認知症サポーターステップアップ研修を開催し、33名が市社会福祉協議会のボランティアセンターに登録しており、今後もこの研修を継続するとともに、修了者による認知症カフェの立ち上げやボランティアスタッフとしての参加を促すなど、地域での裾野を広げる活動につなげていく。
設置数については、第6期高齢者保健福祉計画における目標数である10カ所の早期達成を目指しており、今後の拡充に向けて、30年度からの第7期同計画策定に向けた協議において、地域の状況を踏まえた新たな目標数を具体的に検討していく。
【質問】認知症初期集中支援チームの設置について聞く。
【答弁】平成28年度は、認知症ケア実務経験が3年以上の医師1名と、保健師や看護師をはじめとする専門職2名以上の計3名以上で支援チームを構成し、直営と委託の2チーム体制でスタートする。
初期支援の対象者は在宅の40歳以上で、認知症が疑われ、医療サービス等を受けていない人等としている。対象者の把握については、各地域の高齢者支援センターに寄せられた情報をもとに判断していき、具体的な取り組みとしては、対象者への医療機関の受診の動機付けや医療・介護サービスの利用等についての支援を行い、期間は、安定的な支援に移行するまでの最長6カ月程度としている。
支援チームの体制については、29年度末までに3チームを目標としているが、相談件数に応じて検討していく。
(3)待ったなしの農業振興
本市では、平野部での水稲栽培や野菜の施設園芸、中山間地域での野菜の露地栽培や果樹栽培など、地域の特性に応じた多様な農業が展開されています。
しかし、全国的に農業者の高齢化や減少が進み、耕作放棄地も増加するなど、連鎖的に課題が発生しており、本市も例外ではありません。
平成28年2月にTPP協定が締結され、今後地域間競争の激化も予想されるなか、本市の特色を生かした農業振興の仕組みづくりが求められています。
【質問】本市の耕作放棄地対策について聞く。
【答弁】これまで農地中間管理事業による農用地等の集約・集積、農地の再生作業や土壌改良に取り組んできたが、今般の農業委員会法の改正により、農業委員会の業務として、担い手への農地利用の集約化や耕作放棄地の発生防止等が明確化された。
こうした活動を行う農地利用最適化推進委員を農業委員会が新たに選任することとなり、同委員と農業委員の連携が本市の農業振興に寄与するものと期待している。
【質問】農林水産物の販路拡大策について聞く。
【答弁】現在策定中の第12次農業基本計画において、農林水産物の販路拡大に本格的に取り組むことにより、農家の所得向上を図ることとしている。
平成28年度は、地方創生加速化交付金を活用し、有利な農作物を新たに栽培し、加工販売に取り組む。この事業を進めるに当たり、28年2月に農林水産物を活用した商品開発や販路開拓、市場調査等の業務について、高知県食品工業団地事業協働組合との連携協定を締結した。
併せて、中山間地域において、2次加工まで行うスイーツの開発や搾汁後のユズの皮から精油し、飲料や化粧品等に活用する取り組みを支援していく。
また、開発された商品をこれまで以上に大都市圏での展示会に積極的に持ち込み、バイヤーにつなげ、6次産業化や地産外商を推進していく。
(4)「伝える」から「伝わる」へ
近年、少子高齢化や情報化社会の進展など社会状況の変化とともに、市民ニーズの多様化や新たな情報媒体の普及なども進み、行政に求められる広聴・広報の在り方は大きく変化しています。
本市では、昨年度に庁内のワーキンググループを設置し、今後の広聴・広報活動について検討するとともに、平成28年度から広聴広報推進室を新設し、取り組みを強化していくこととしています。
【質問】本市が目指す広聴・広報活動の在り方について聞く。
【答弁】平成27年度の市民意識調査によると、市政に対する要望等があっても「何もしない」との回答が5割を超えており、広聴についてはいつでも、気軽に、簡単に要望や提案等ができる機会の拡充が必要である。同じく、20歳代の約3割が広報「あかるいまち」を読んでいないとの回答があり、広報についてはタイムリーで分かりやすく、手に入れやすい情報発信が必要である。
このことから、市民の市政に対する関心を高めること、そして情報共有や相互理解を進め、市政への市民参画を促すことを基本的な考え方として、「伝える」広聴・広報から、「伝わる」広聴・広報へ転換し、行政と市民のキャッチボール型の広聴・広報を展開していく。
【質問】広聴・広報活動の新たな取り組みについて聞く。
【答弁】広聴の取り組みとして、市民ニーズを確認する必要がある重要なテーマについては、地域懇談会や企業・市民団体を対象とする出前講座の実施などによって情報共有を行い、要望や提案を直接受ける機会を充実させていく。
広報については、「あかるいまち」のカラー化や、ターゲットを絞った新たな広報紙の発行に取り組む。
そして、広聴・広報の正しい理解とスキルの向上を図るために、職員研修の充実も検討する。また、庁内の調整を踏まえ、平成29年度に、広聴広報推進室を専門の課へ格上げすることを考えている。
(5)市役所の御案内はこちらで ~ワンストップサービスの充実に向けて~
市役所で各種手続を行う時、窓口が分からず困った経験をお持ちの方もおられると思います。
特に福祉部門は窓口が分散しており、手続が煩雑になっています。
そのため、平成30年度末の完成を目指す新庁舎においては、市民に分かりやすく利用しやすい庁舎を基本理念としており、ワンストップサービスの実現に向けて検討を進めています。
【質問】案内機能の充実について聞く。
【答弁】新庁舎においては、来庁者のスムーズな申請手続等につなげるため、コンシェルジュ機能を持つフロアアドバイザーの導入や総合案内の設置を図ることとしている。
現在の仮庁舎や第2庁舎に総合案内を設置することはスペースの都合上難しいが、フロアアドバイザーについては、新庁舎の供用開始に先立ち、平成30年度からの試行的な導入に向けて検討していく。
【質問】窓口機能の充実について聞く。
【答弁】市民の窓口手続負担の軽減や、窓口間の移動距離と待ち時間の短縮を図るため、申請様式の見直しや住民票をはじめとする各種証明等の発行窓口の一元化、また、高齢者福祉や子育て支援などの部門別の総合窓口の設置を検討しており、必要となる情報システムについても、業務横断的な一括処理機能等を持たせることとしている。
こうした取り組みには、集約する業務範囲の設定が必要なことから、窓口対応課の職員で構成する新庁舎建設検討委員会窓口サービス部会においてそれらの検討を行い、窓口運営を支援するシステムについて具体化していく。
また、地域の窓口センターについても、総合窓口での業務範囲やシステムの概要を決定した後、市民ニーズや費用対効果も踏まえ、機能拡充に向けた組織体制を検討していく。
4 休憩室
“柔らかい力”で
朝の連続テレビ小説「あさが来た」が終わりました。女性が思ったことを言うことさえ戒められていた時代に、家族など周囲に支えられながら、炭鉱や銀行業等を起業、その経営に携わる傍ら日本初の女子大学を創設。「みんなが笑って暮らせる世の中をつくるには女性の“柔らかい力”が大切」と語る「あさ」の人生に、皆さんもつい引き込まれたことでしょう。
「あさ」に続く人々の努力の上に、今では日本国憲法に男女平等がうたわれ、1985年国連女性差別撤廃条約を批准、男女共同参画基本法、女性活躍推進法などで女性の社会的立場は当時とは比べものにならないほど前進し、本市でも3月に「男女共同参画推進プラン2016」を策定したところです。
しかし、世界の男女の格差ランキングで、日本は145カ国中101位と先進国では最低。
今年3月には国連女性差別撤廃委員会から、民法の規定や賃金格差の是正など政府の姿勢を問う厳しい勧告がなされました。「保育園落ちたの私だ!」と1人のママの呟きにたくさんのママ達が声を上げ、待機児童解消へ政府を動かす世論を巻き起こしました。
政治と無縁ではいられない日々の暮らし。“柔らかい力”で、男性も女性も生き生き暮らせるまち高知にしていきましょう。
(議会広報委員 浜口佳寿子)
5 3月定例会を振り返って(会派の意見)
市民クラブ
まっこと高知がえいちや そんな高知市をめざして!
岡崎豊議員は代表質問を行い、市長の政治姿勢を中心に、市政の主要な課題についてただしました。財政の健全化を維持する視点から新年度の予算編成に関して、市長は「集中改革期間」になり、地方行財政改革を集中的に進める方針を提示。子育て支援策については、医療費の無料化を小学6年生まで拡大し、新生児の聴覚検査を無料で実施する。手話言語条例の制定により、手話を言語として普及することや、障害者差別解消法にも対応するとしました。
浜田拓議員は、平成27年9月に安倍政権が安全保障関連法案を十分な国会議論をせず強行採決したことに反対の立場を表明。「憲法第九条違反の戦争法」と断じました。為政者はその声を真剣に受けとめるべきだが考えやいかに!市長は「わが国を取り巻く状況は厳しく、さらに議論を重ねるべき」と答弁。
深瀬裕彦議員は、市街化調整区域における地区計画策定の運用基準で、地区計画が策定できる地区を宅地的造成が行われている地区に制限しているが、都市計画マスタープランの方針では、活力維持が求められている地域や幹線道路周辺も掲げられているため矛盾することなど4点について質問。
日本共産党
市民不在の大型事業優先に対峙(たいじ)。新図書館西敷地は緑の空間に。待機児解消に保育士処遇改善へ。
代表質問に岡田、一般質問にはた、浜口、下元、下本の各議員が登壇し、新年度予算等について、経済的に深刻さを増す市民の負担軽減、暮らしを支える立場から、市民に投資的事業の長期的財政計画を示し、市民参加による市政運営を求めた。
新図書館西敷地について、中心市街地活性化を理由に、市民の声を聞かぬまま民間による高層施設の建設を急ぐことは問題と指摘。市民が緑の空間を体感した後に検討することを提案。
保育士不足により待機児童が急増しており、臨時保育士がクラス担任となる実態を示し、保育士の増員と処遇改善を求め、賃金引き上げと雇い止め期間短縮の答弁を引き出した。
市の指導に従わない無届けでの土地造成の実態を指摘し、土地保全条例の改正を求めた。
水道事業では、本来行うべき一般会計からの繰り入れをせず、10年間で約8.8億円もの国の支援を失った責任を明らかにし、水道財政の切迫を理由とする安易な値上げは容認できないと、修正案の提案を行った。
新風クラブ
し尿収集と不燃物処理に係る2法人2施設の統合移転を検討!
◆代表質問 和田勝美議員
わが会派は不断の行政改革として執行組織の改革を提言しており、前回に引き続き今定例会でも、環境事業公社と再生資源処理協同組合の組織統合と施設整備をただした。これに対し執行部は「両施設とも南海トラフ地震の津波リスクが大きく、早期の移転が必要と認識している。移転用地の確保が大きな課題だが、新年度には専門職員を配置して検討を進める」と答えた。
◆個人質問 清水おさむ議員
清掃工場売電の未収金問題でリスク管理の甘さを指摘。市長は組織的なリスク管理に課題があったことを認めるとともに「28年度の入札から、10%の契約保証金を課すことや支払期限を超過した際の契約解除規定を設けた」と改善策を示した。
◆個人質問 平田文彦議員
地元での認知症サロンやカフェの実践経験を踏まえ、認知症初期集中支援チームについてただした。執行部は「来年度から医師ら3人以上で構成する直営と委託の2チーム体制で始め、今後の相談件数に応じて拡充を図っていく」と答えた。
公 明 党
大衆の声に耳を傾け、市民の願いを市政に届ける公明党
寺内憲資議員は、28年度予算等について代表質問を行いました。また、全日本海員組合から公明党に対して要望のあった、住民サービスの享受に制限を受ける船員に対する個人市民税の減免について、既に実施中の四日市市を例に質問を行いました。市長からは、全国市長会を通じて関係省庁に働きかける旨の答弁がありました。
西森美和議員は、COP21パリ協定を踏まえ前例踏襲でない温暖化対策を求め、特に地元の低炭素商品の地産地消と地産外商を促進する環境産業の認定制度を提案し、地元の環境産業にスポットを当て検討を進める旨の前向きな答弁を得ました。
高木妙議員は、胃がん検診や地方創生に必要な広聴・広報機能の充実、官民協働によるヘルスケア産業の取り組みについてただしました。市長は、政策連携機能強化の必要性や、広聴・広報機能を高める取り組みについて前向きな答弁をしました。
新こうち未来
新年度からスタートする機構改革に期待。個人質問には氏原嗣志議員が登壇。
平成28年度から総務部に広聴広報推進室、財務部には財産政策室が新設されることとなった。広聴広報推進室においては市民により分かりやすい情報発信がなされ、財産政策室では公共施設マネジメントの具体的な計画が策定される。いずれも新たな感覚で大いに進めていただきたい。
個人質問では氏原嗣志議員からの、TPPによる本県農業への影響をどのように分析し、市民に説明していくのかとの問いに対し、新たに創設された国のTPP関連事業などの周知を通じて不安の払拭に努めるとの答弁があった。その他、浅草の「まるごとにっぽん」における本市ブースのさらなる充実や農業委員会制度改正に伴う質問を行った。
みどりの会
近森議員が新観光資源を発信
高知市旅館ホテル協同組合の主催で拉麺(らーめん)王国宣言を行いました。
高知市のラーメンは統一されたものでなく百花繚乱。
老舗店舗や若手精鋭店舗が自慢の味を争う、まさにラーメン戦国時代。
高知市の新観光資源、拉麺王国宣言!!よろしくお願いします。
7 3月定例会に提出した意見書
全会一致で可決した意見書
⑴地方公会計の整備促進に係る意見書
各自治体における地方公会計は、平成27年1月の総務大臣通知により、27年度から29年度までの3年間で、統一的な基準による財務書類を作成するよう要請されている。
よって、この通知に基づき、高齢化や人口減少の課題を抱えている各自治体の厳しい財政状況を勘案し、可能な限り早期整備ができるよう、実務面でのきめ細かな支援を実施することなど2項目を、国に強く要請する。
⑵ビキニ水爆実験に関する元乗組員等への健康影響について国の公式見解を求める意見書
1954年のビキニ水爆実験に遭遇した船舶約1000隻のうち3分の1が高知県の船籍であると言われているが、第五福竜丸の乗組員以外に船員保険の適用を受けた事例はない。
高知県の高校生が、31年前から実態解明に努めてきた結果、厚生労働省は実験に遭遇した漁船等延べ550隻の検査結果を含む公文書を開示した。また、高知県の要請もあり、同省は開示文書の研究チームを設置し、科学的検証を行っている。
よって、乗組員等への健康影響に関して国の公式見解を取りまとめ、健康への影響が認められる場合には適切な救済措置を実施するよう、国に強く求める。
⑶無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書
わが国の電線地中化の実施率は、欧米やアジアの主要都市と比較して著しく低い状況である。無電柱化の取り組みは、道路交通の改善や良好な景観形成による観光振興、南海地震対策として街全体の防災性の向上などの点で重要である。
よって、電線地中化工事を総合的、計画的かつ迅速に推進する、無電柱化の推進に関する法律の整備に早急に取り組むよう、国に強く求める。
賛成多数で可決した意見書
⑷女性差別撤廃条約批准国として条約上の責務を積極的に果たすことを求める意見書
平成27年、最高裁判所は、民法の夫婦同姓を強制する規定について、憲法に違反しないとする判決を下したが、制度の在り方は国会の議論に委ねた。
同時に、女性だけに課せられた離婚後6カ月の再婚禁止については、100日超の期間を違憲とする判断も示した。
こうした中、国連の女性差別撤廃委員会は、28年3月、夫婦同姓の強制や結婚最低年齢の男女差などの民法の差別的規定が改正されていないことに対して、改正の即時措置を勧告した。
よって、女性差別撤廃条約の締約国として、条約上の義務を果たすことを、国に強く求める。
⑸寡婦控除を未婚の母子世帯まで拡大することを求める意見書
寡婦控除は、未婚の母子世帯には適用されない。その影響は、所得税だけでなく、保育料や公営住宅の家賃の算定等にも及ぶため、未婚の母子世帯と他の母子世帯との経済的な格差は拡大している。
また、民法の分野では、法改正により摘出子と非摘出子の相続は同等になっており、税制の分野でも法改正が必要である。
よって、寡婦控除を未婚の母子世帯まで拡大する法改正を早期に実現することを、国に強く求める。
⑹奨学金制度の充実等を求める意見書
奨学金については、大学生の5割超、大学院生の6割超が受給している。
一方で、就職難や非正規労働の増加などが原因で、奨学金の返還ができずに苦しむ若者が急増している。
よって、学習意欲と能力のある若者が家庭の状況にかかわらず進学し、安心して学業に専念できる環境をつくるため、大学生等を対象にした給付型奨学金制度を創設することなど4項目を、国に強く求める。
⑺TPPの影響に関する国民の不安を払拭し、対策の確実な実行を求める意見書
平成28年2月に署名されたTPPにより、わが国では輸出が拡大し、経済再生に資することが期待される一方で、地域の基幹産業である農林水産業への影響が懸念されている。
このため、政府は、27年11月に国民の不安や懸念を払拭し、農林水産業を成長産業として支援するため、TPP関連政策大綱を決定した。
よって、同大綱に基づく法整備と速やかな予算執行をはじめ、農林水産業の体質強化を念頭に、中長期的な対策を講じることなど4項目を、政府に求める。
⑻児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書
児童虐待により、幼い命が奪われる深刻な事態が続いている。また、家庭や地域における養育力の低下、子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、児童虐待の相談対応件数は増加の一途をたどり、複雑・困難なケースも増加している。
よって、児童虐待の発生予防から発生時の迅速かつ的確な対応、自立支援に至るまでの一連の対策強化のため、早期に児童福祉法等改正案を国会に提出するとともに、子育て世代包括支援センターを法定化し、全国展開を図ることなど6項目を、政府に強く求める。
否決した意見書
⑼TPP協定を批准しないことを求める意見書
8 人事議案
3月定例会最終日の25日に、市長から副市長、教育委員会委員、固定資産評価員、固定資産評価審査委員会委員の選任議案が提出され、それぞれ同意しました。
副市長
吉岡 章(よしおか あきら)
教育委員会委員
森田 美佐(もりた みさ)
固定資産評価員
前島 弘俊(まえじま ひろとし)
固定資産評価審査委員会委員
大崎 彰一(おおさき しょういち)
9 委員会の活動(2月1日から4月30日まで)
常任委員会
経済文教委員会
3月定例会 17、18、22日に、市立市民図書館条例の一部改正議案など15件の議案と請願1件の審査を行いました。
平成28年度一般会計予算および28年度産業立地推進事業特別会計予算は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決し、請願1件の結果を出しました。また、市立小・中学校の今後の在り方に関する検討委員会の報告書についてなど4件の報告を受けました。
建設環境委員会
3月定例会 8日に、訴訟の提起についての議案の審査を行い、賛成多数で可決しました。
17、18、22日に、空家等対策協議会条例制定議案など17件の議案の審査を行いました。
平成28年度一般会計予算および28年度水道事業会計予算は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決しました。
その後、提出された28年度一般会計予算に対する附帯決議案は否決しました。また、2016高知市緑の基本計画(案)についてなど4件の報告を受けました。
厚生委員会
3月定例会
17、18、22日に、手話言語条例制定議案など31件の議案の審査を行いました。
平成28年度一般会計予算、28年度国民健康保険事業特別会計予算および国民健康保険条例の一部改正議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決しました。また、地域福祉活動推進計画の取り組み状況について報告を受けました。
総務委員会
3月定例会
17、18、22日に、特別会計設置条例の一部改正議案など31件の議案と陳情1件の審査を行いました。
平成28年度一般会計予算は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決し、陳情1件の結果を出しました。また、公会計制度に基づく26年度財務書類についてなど6件の報告を受けました。
特別委員会
都市再生調査特別委員会
2月4・5日
石川県金沢市の「シェア金沢」にてCCRC(生涯活躍のまち)、東京都新宿区にて道路占用特例を活用した取り組みの視察を行いました。
3月3日
地域公共交通網形成計画についてなど2件の報告を受けました。また、中間報告について協議を行いました。
3月7日
本会議で中間報告を行いました。
行財政改革・新庁舎整備調査特別委員会
2月22日
公共施設マネジメントの進捗状況についてなど2件の報告を受けました。また、中間報告について協議を行いました。
3月7日
本会議で中間報告を行いました。
3月31日
指定管理者選定手続ガイドライン案についてなど3件の報告を受けました。
南海地震等災害対策調査特別委員会
2月26日
三重防護についてなど2件の報告を受けました。また、中間報告について協議を行いました。
3月7日
本会議で中間報告を行いました。
10 高知市議会からのお知らせ
(1)録画DVDの貸し出し
本会議の中継放送を録画したDVDの貸し出しを行っています。
貸し出し準備に時間を要するため、ご希望の方はあらかじめ、議会事務局までお申し込みください。
電話823-9400
(2)インターネットによる本会議の録画配信
過去1年間の本会議(定例会)について、インターネットで配信しています。
高知市ホームページから議会中継(録画)専用ページに入ると視聴できます。
会議日や質問議員名、発言内容の語句等からの検索も可能です。
(3)請願・陳情の出し方
市の行政などに対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情はその必要がなく、審査は請願と同様に取り扱われます。
文書は市議会議長宛てに1通提出してください。
なお、定例会ごとに締め切りがあり、それを過ぎた場合は次の定例会からの審査になりますので、ご注意ください。
請願(陳情)書の記載例
○年○月○日 高知市議会議長 ○○ ○○ 様 (代表者の)住所○○○○○○○○○○○○ (代表者の)氏名 (個人の)印 紹介議員氏名 印 ※ 陳情は紹介議員不要です。 ○○○に関する請願(陳情) . 趣旨・理由
|
(4) 会議録の閲覧
3月定例会本会議の会議録は6月上旬にできる予定です。
本町仮庁舎1階の情報公開センター、同6階の議会図書室でご覧になれます。
また、高知市ホームページ上で、本会議は平成6年12月定例会以降、委員会は16年4月以降の会議録をご覧いただけます。
11 会派の構成と電話・ファクス番号
市民クラブ (8人)☎823-9402 FAX 802-3055
日本共産党 (7人)☎823-9404 FAX 823-9558
新風クラブ (7人)☎823-9401 FAX 871-2811
公 明 党 (6人)☎823-9403 FAX 871-2485
新こうち未来(5人)☎823-9406 FAX 822-8119
みどりの会 (1人)☎823-9476 FAX 823-9350※
※議会事務局直通のファクス番号です



